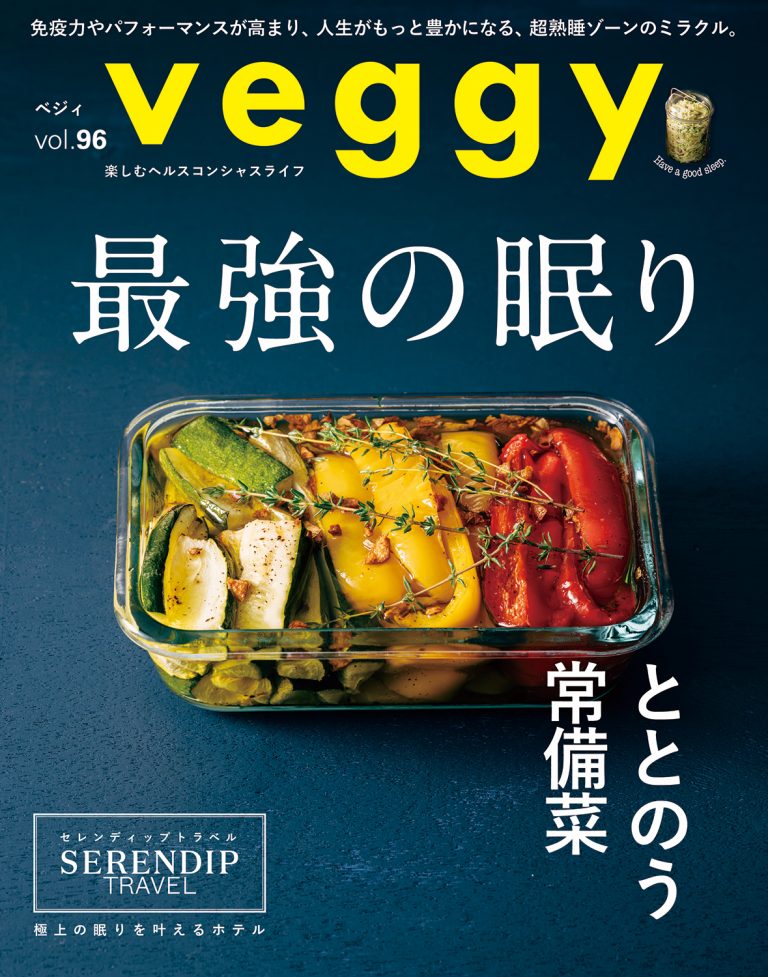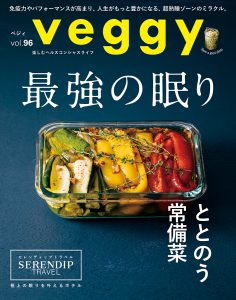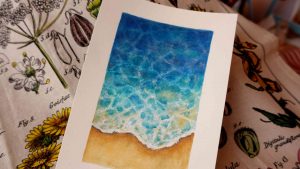コマクサという高山植物がある。生でみたことはまだないが、夏にピンク色の可憐な花を咲かせる。
コマクサが生息するのは、つよい寒風が吹くなかを礫(つぶて)と呼ばれる小石がはげしく移動するような、荒涼とした砂礫地(されきち)だ。あまりに過酷なためにほかの植物が生育しないような環境をわざわざえらんで、コマクサは咲く。十センチほどのちいさな見た目からは想像できない一メートルにも及ぶことのある茎や根を地下深くへと伸ばしているが、それもきびしい環境で力づよく生き抜くためだ。
そんな孤高の花の名前がつけられた東京郊外の幼稚園に、おなじ団地に住むちーちゃんとりょうたくんと通っていた。人生で初めてできた友人であるふたりとはほぼ毎日一緒に過ごしていたが、年長にあがる年にちーちゃんは鎌倉へ移り、小学校へあがる前に私も伊豆へ越した。三人一緒だったのは、じっさいは年中組の一年間だけだった。
小学生になってからちーちゃんもりょうたくんも伊豆に会いにきてくれたが、それ以来会うことはなかった。
一昨年私が越してきた鎌倉の家が、たまたまちーちゃんの実家から歩いてすぐのところだった。ちーちゃんは実家を出てはいたが、今も鎌倉市内に住んでいると聞いていたので、また会えるかなと思っていた。
梅雨の合間の晴れた日、ついにちーちゃんと再会した。うちに来てくれて、十年近く使っている年季の入った食卓テーブルで私の作ったごはんを一緒にたべた。ちーちゃんはすこしも変わっていなかった。
* * *
ちーちゃんと私は泥団子作りに夢中だった。
幼稚園時代の記憶のほとんどは霧のむこうにあってほとんどこちら側へ姿をあらわすことはない私だが、くる日もくる日も熱心に泥団子を作っていた感覚だけはぼんやり思い出すことができる。
園の端っこにひさしのようなものがあって、通園バスが止まっていた。雨が降るとぬかるむその辺りが、私たちの泥団子工場だった。ふたりで、りょうたくんと三人で、よく作った。ほかの子と一緒のときもあった。できあがった泥団子を地面に落として、だれのがいちばん壊れないか競うあそびをしていたんだよねえ、とちーちゃんがなつかしんだ。
話をしながら、ちーちゃんは記憶力が抜群で、冷静な観察者であり、子どもながらにするどい分析力に長けていたことを知った。過去のある場面の周囲の状況やそこにいた人のようす、そのときじぶんが抱いた感情の流れなどを鮮明に記憶していて、それらをすっと取り出すことができる。
ちーちゃんがたのしそうにおしえてくれた。私、今でも忘れないんだけど、めぐちゃんは泥団子の作り方につよいこだわりを持っていて、ものすごく上手につるつるできれいで頑丈な泥団子を作ったの。そのためにどのくらいの水をふくんで、どのくらいの硬さに調節したらいいか、明確な基準を持っていたよ。
そうだった。たしかにそうだった。あの頃、とびきりの泥団子を作ることが生きがいだった。友だちよりも昨日のじぶんよりも、だれよりもきれいで、落としてもけっして割れない頑丈な泥団子を、どうしても作らなければならなかった。
* * *
その頃、すこしづつじぶんの心が折れていく音が聞こえるようになっていた。幼稚園で過ごす時間はたのしかったが、三つ下のきょうだいが生まれてから家に居場所がないと感じていた。
一歳の誕生日に生死の境をさまよったこともある体の弱いきょうだいの面倒を、単身赴任で家にいることがめずらしかった父のぶんまで母はひとりで見なければならなかった。きょうだいの看病で手一杯な母は、いつも不安と恐怖に支配されているように見えた。そして健康な私に対してきびしく接した。そのたびに自分がすこしづつすり減っていくような感覚があった。
きょうだいが生まれる前とあととでは、別の家族のところへやってきたみたいになにもかもが変わってしまった。両親は精一杯だったのだと思うが、余裕のない母によく叱られ、父に甘えることもできない私は、いつもさみしかった。
家族がなかよく一緒にいることができないなら、だれもいない場所に行ってひとりでいたい。だんだんそう思うようになった。コマクサのように。
めぐちゃんが安心した顔してるときね、お父さんが帰ってきてるんだなあってわかったよ、とちーちゃんが穏やかな顔でおしえてくれたとき、ちーちゃんの洞察力に関心しながら、なにかが堰を切ったようにあふれだしそうになるのを感じて身構える自分がいた。私は五歳の私に、絆創膏を用意してやらなくてはならないと思った。
それでもちーちゃんが鈴の鳴るようなやわらかい声で語ってくれる古い物語に、耳を傾けずにはいられなかった。
ちょっとしんどいかもしれない。
一度だけだったと思うけど、もしかしたら泥団子を作っていたときだったかな、めぐちゃんが私とりょうたくんの前でそう吐露したことがあってね、とちーちゃんが言った。自分がそんなことを誰かに言っていたなんて信じられなかった。思い出したい気持ちと思い出したくない気持ちがぐるぐるに絡み合ってうるさい洗濯機にかけられているみたいだった。
しんどいんだけど、そういう気持ちをお母さんには言えないし、どうしたらいいかわからない。ちーちゃんの喉から聞こえてくる五歳の私の声をどう聞いたらいいのかわからず、胸の奥からきつく雑巾をしぼっているような音が聞こえた。このまま中身のわからない包みの紐をそろそろ解いてしまえば、中から次々と手に負えない生き物がでてきそうだった。ちーちゃんは仏様のように落ちついた声でつづけた。
「そしたらね、めぐちゃんはさ、お母さんに嫌われないようにいつも気を使っているから、きっとそれで疲れちゃうんだよね、ってりょうたくんがやさしくなぐさめたの。そんなふうにはっきり言語化できるの、すごいなって思った。私はそう思ってもうまくことばにできなくて、黙ってそばにいるしかできなかったんだけど」
大袈裟でなく、足元からくずれ落ちそうになった。すっかり忘れていたはずの記憶にごうっ、と火が灯った。かけてもらったその言葉こそはっきりとはおぼえてはいないものの、ふたりがいつもそばにいてくれた体の感覚が急に熱を帯びてよみがえったのだ。
たった五歳。五歳ですでに、こんなにやさしい世界に私は生きていた。そうと知り、ふたりへの感謝で胸があふれた。ふたりがいてくれたことで、果たしてどれだけ救われたんだろう。どれだけひとりじゃないと思えただろう。大人の私が貼るまでもなく、泥団子工場ですでにふたりが貼ってくれていた絆創膏に私はずっとまもられていた。
私にはふたりがいるから大丈夫だし、これからも安心して忘れていたらいい。こっちは振り返らず、そのまま前だけ向いていればいい。ようやく口を開いた五歳の無口な私は今の私にそれだけ言うと、くるっと背を向けて安心したようにまたふたりと泥団子あそびを始めた。
* * *
なぜつるつるできれいで、けっして壊れない泥団子を作る必要があったのか。コマクサがなぜ、だれもいない荒野をえらんで咲くのか。その自然の法則のようなものが、二十数年ぶりにちーちゃんに会えたことでわかった。生き物は生きている限り、つよくなろうとする。割り当てられた命を生きつづけるためにつよくなる必要があり、つよくありたいと願う。だから頑丈な泥団子を作り、荒野にこそ根を張る。私には幸運なことに、つよくなるために支えてくれるちいさな友人がそばにいた。
ひとりきりで生きていけるような強靭さはないが、未だにコマクサのようなところが私にはある。できるだけ過酷で、逆境で、ゆえに人のいない場所を好む。そういうところにいたいというよりは、そちらのほうが馴染みがあるために安心できることが多かったり、生きていることを実感できたりする。
でも、その荒涼とした場所に太陽が昇らないわけではない。なにもなく、ほかにだれもいないからこそ、太陽が昇ればさえぎるものがない。その光をまっすぐ受けることができる。ちーちゃんとりょうたくんはこの先も私の荒野になんども昇る太陽のような人たちだ。
泥団子は今も作りつづけている。まわりから見ればただ真っ黒でなんの価値ももたないかもしれない泥のかたまりに、どうにか命を吹き込もうと奮闘している。力のいることでもあるが、そのことをどこかでたのしんでいる。そうとしか生きられない人間がいてもいいと面白がってもいる。そういうじぶんになれたのは、ふたりを始め私をここまで運んできてくれたすべての人との出会いがあったからだ。そのおかげもあって、落としてこわれてしまういびつな泥団子ができてもいいと思えるようになった。どうせ一生やっていくことなのだから、一生懸命作ったものがもしこわれてもまた作るのだし、それまでの経験がけっして無駄になることはない。
反省するのは、いつもじぶんのことで精一杯だったこと。あの時、ちーちゃんとりょうたくんにおなじようにつらいことがあったとしても、気づいてあげられていた自信がない。
そんな私でもそばにいてくれて、寄り添ってくれていたふたりに、今もう一度ありがとうをいいたい。近くにいるちーちゃんにはまた会えたらうれしい。ちーちゃんのように思慮深くて、前向きでいるために努力していて、うそのない透き通った声で話す人が人生最初の友人だった私はほんとうに幸福だったと思う。りょうたくんにも、どこかで会えればお礼をいいたい。でも今は今の生活があるだろうから、無理にとは思わないし、このまま会えなくてもいい。
ふたりのおかげで、人はいつどこでだれにたすけられて今があるかわからないということに、改めて気づくことができた。それは、そうやって生かされてきたありのままの自分でいながらできることを自分の場所で淡々としていきたい、と願う気持ちに繋がっている。誰もいない荒野をえらんで咲くコマクサも、おなじことを思うのではないだろうか。

写真・文 関根 愛(せきねめぐみ)
俳優、執筆、映像/作品制作を行う傍ら、ライフワークとして食に取り組む。マクロビオティックマイスター/発酵食品マイスター/Vegan検定1級。2021年度veggy公式lifeアンバサダー。鎌倉在住。
Youtube:鎌倉の小さな台所から
Instagram:@megumi___sekine