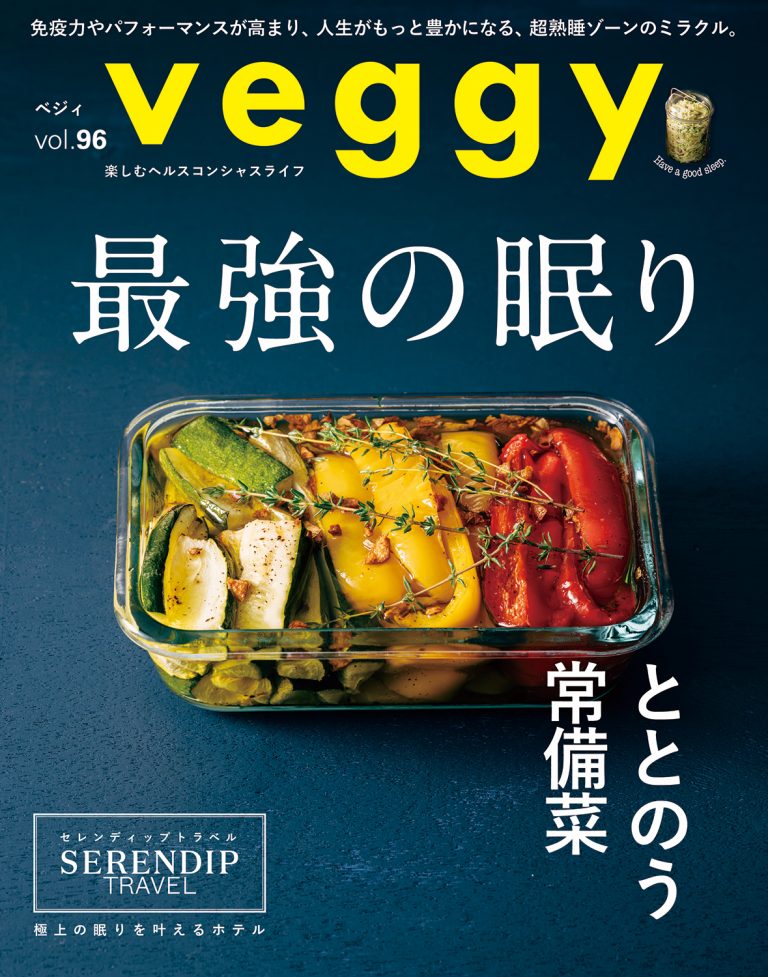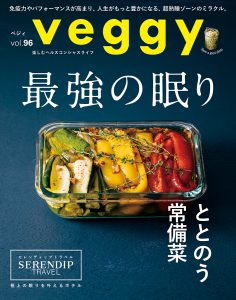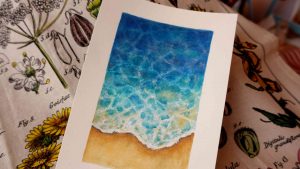時を超えて
鎌倉で迎える二度目の新年。とくべつどの宗教を信じているなどもないので、気ままにいくつかのお寺や神社へ足を運んでいる。元旦は去年のように八幡宮を訪ねてみたけれど、長蛇の列だったので、北鎌倉の建長寺と明月院へ。どちらもひっそりした正月らしい静けさが心地よく、厳かな新年の始まりとなった。帰りに扇ヶ谷にもあるアマザケスタンドの北鎌倉店を通りがかったので、ほうじ茶甘酒を作ってもらう。ここの甘酒にはふわふわのホイップクリームがのっているのだけれど、牛乳ではなく甘酒を特殊な機械でホイップにしているらしい。自然の甘味だけなのに、チョコレートみたいにとっても甘い。

ほかにも散歩がてら、五五二年発祥の腰越の龍口明神社や、鎌倉駅からほど近い本覚寺を初めて訪ねた。本覚寺は商売繁盛の神様でもある。「この地の人々に昔から親しまれています」という文句が気になった「にぎり福」という可愛らしいお守りをふたつ、買ってみることに。福、愛、健、財、学の五つが握り込まれているという小さな石のようなもので、それぞれに手書きらしき温かな筆致でほほえんだ顔が描かれている。毎日握ってあげることで、福がやってくるらしい。「人から言われた通りのことを腑に落ちていないのにすること」が苦手なあまのじゃくなわたしはめずらしくすなおになって、家をでるときに忘れず握れるようにと玄関先に置いてみる。親指の爪ほどのにぎり福をつまんでてのひらにのせ、やさしく包んでみる。つられてまぶたも閉じてしまう。少しすると、あたりまえだけれどてのひらの中がじんわり温かくなってきて、にぎり福が心地よさそうにふるえ出す。そして気づく。福はどこか外からやってくるのではなく、このてのひらのなかにすでにあるのだということを思い出すために、握る仕かけになっているのだと。
「ないと思っているものは、ほんとうは案外そばにすでにある」そんなことを去年あたりから頻繁に感じるようになった。そばにあるということは、ぼやけて姿をとらえにくいとか、あるいは一部しか見えていないということなので、あること自体に気づきにくいだけ。じぶんの視点を引いてみたり変えてみたりすることで知っていると思っていることがぜんぜんちがう顔を見せはじめることを、そんな発見のチャンスが散りばめられた毎日を生きていることを、いつもうれしがって生きていたい。
ないように思っていてじつはあるのは、未来の時間についても同じではないか。わたしたちはじぶんがいつ死んでしまうかさえわからないほど未来についてなんの情報も持っていない。それゆえに未来はまっさらでまだなにも決まっていないのだと思ったりする。けれど、未来はほんとうにまだないのだろうか。わたしたちが知らないだけですでに、未来は未来でつつがなくやっているんじゃないだろうか?そんな気がする。そして、その光景をほんの少し思い出すことができれば、逆算して今をどう生きるかが定まってくると思うのだ。

時間といえば、形を変えることのない太陽とくらべると絶えず満ち欠けという変化をしなやかにくり返しながら月でありつづけている月は、まるで時間そのものだ。あるいは月は時間の貯蔵庫みたいなものかもしれない。とうに過ぎていった過去もこれからいく未来も、すべての時間が月にある。時の供給源のようなもの。ひときわ明るい月をある日ぼんやり眺めていて、その力に圧倒されてなんとなくそんなことを思ったことがあるのだが、どうやら今から千年も昔の世でとある人が同じようなことを思ったらしい。最近になって古典文学に興味を持ち、今までちゃんと読んだことのなかった「枕草子」を手に取った。延々とつづく宮中の描写に飽きてきて途中から流し読みしていると、ある箇所でページをめくる手がとまった。「月の明かきはしも、過ぎにしかた、行末まで思ひ残さるることなく、心もあくがれ、めでたく、あはれなること、たぐひなくおぼゆ。」
これは、月が明るいのは、過去や未来まで心に思い残されることがなく、心が身に添わないで過去や未来に飛び去り、すばらしいこと、しみじみと考えさせられることなど、くらべるものがないくらいすばらしいと思う、という意味なのだそうだ(田中重太郎訳註)。月をみているとき体はここにあるのに心は過去にも未来にも飛んでいくというのは、起きたこともこれから起きることも、月はあらゆる時間を知っている、ということではないだろうか。よくもこんなにことこまかに日常のことを記す力があったなあ、とため息がでるほどの長い長い文章の海でこの一文に巡りあった時、思いもよらない場所でとくべつな友達と手を取り合えたみたいでうれしかった。その人ははるか昔にこの世界を去った人で、わたしは今たまたまこの時代に生きていて、そういう者同士が時を超えてひとつの温かい気持ちをわけあっている。体は同じ時を生きていないのに、かの人が二千二十三年にやってくることも、わたしが平安の世にいくこともできてしまう。どうしてこんなふうに時を超えられるんだろう。
たましいと呼ばれるもの
「かまくら暮らし歳月記」を書いてもうすぐ一年が経つ。鎌倉の豊かでさりげない四季を通して、とくべつなことの大してない毎日が沢山のとくべつな瞬間からできていることを感じた。とくべつと言ってもそれらの中には決していいことだけがあるわけではなく苦い思いや、もどかしさ、わずらわしさ、時に傷のようなものもふくんでいる。どれもあたりまえに目の前を過ぎ去っていき、今もうここにはない。でも、まったく消えてなくなってしまったわけでもない。ふたたび「枕草子」を引くと、こう書いてあった。「ただ過ぎに過ぐるもの。帆かけたる舟。人の齢。春、夏、秋、冬。」舟も月日も季節も、いちどうごきはじめたものはどんどん加速していく。まばたきの間もないほどあっというまに、目の前を過ぎ去っていく。けれどもただ過ぎに過ぐるものはただ過ぎているわけではなく、「巡る」という大きな運びの一部としていつまでも形を変えながら、ただひたすらにそうであるのだろう。その中でどう生きるか考え、じぶんなりに実践しつづけていく道のりをこんなにたのしいと感じる大人になることができてよかったと思うようになったのは、毎月このようにしてとりとめのないことを綴っていくことができたからだと思う。もしかしたら一千年前のかの人も、どこかでそんなことを思いながら過ぎゆくものに思いを馳せていたかもしれない。
この世からいなくなってしまった人のたましいはどこへいったんだろう、と子どもの頃からふしぎに思っていた。そもそもたましいが何なのかというのも、はっきりとはわからない。でもなんとなく、この世とあの世のあいだで行き来しているような、あるいはやりとりされているもののような気がする。そしてこの世にそれが現れようとする時、この世に残されたあらゆる「文字」の中にその居場所をみつけるかもしれない。たとえそれが個人的な日記や人に読まれるつもりもなく書き散らしたもの、または脈絡のないメモ書きなどでもいい。その「文字」を今読んでいるだれかとそれを残した人の間に何度でも生まれるものをたましいと呼ぶのだとしたら、すごくいいなと思う。
今にも永遠に過ぎ去ろうとする目の前の時間の流れにひたすら身を置き、これからもその見えなくなっていくしっぽをやさしく掴むように「文字」に落としていきたい。姿を変えながら存在しつづける月のように、あちらとこちらを行ったり来たりしながら生きるたましいがいつか安心してこの世の居場所としてくれるような「文字」を残せたらいいなと思う。そのために書き続ける。今ここにある時間、かつてここにあった時間とこれから先もしばらくつづいていく時間、それとすべてが過ぎ去ったあとの時間に愛を込めて、そうしていきたい。一年間お読みいただきありがとうございました。

写真・文/ 関根 愛(せきね めぐみ)
関根 愛(せきね めぐみ)