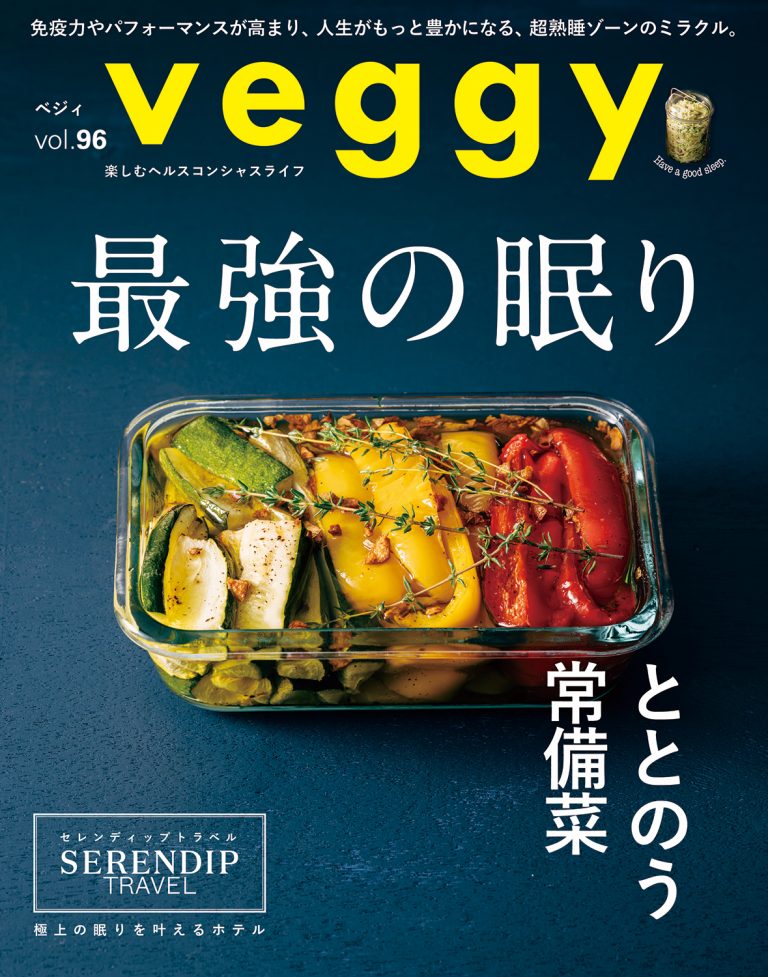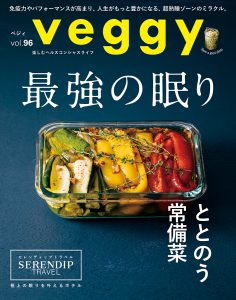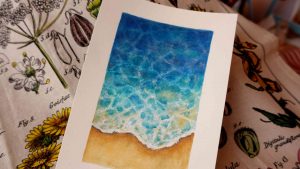– すれちがう春 –
夏に鎌倉に越してきて、長い冬がようやく背中を向け去り、待ちわびた春がきた。さいきんは雨風の日も多かったけれど、これが春を連れてくるのだと思うと今までにないほどわくわくした。
今朝散歩をしていると、採れたての巨大わかめをハワイアンのレイみたいに首から下げ、白い歯を光らせて笑うサーファーのおじさんとすれ違った。その人の歯がずば抜けて白いのか、それとも焼けた肌と真っ黒なウェットスーツのせいで白さが際立っていただけなのかわからないけど、とにかく歯が白いおじさんはどちらかというと、人というよりは首に巻きついたわかめのほうに近い生き物に思えた。人工的なものでごった返した都心の谷底にへばりつくように暮らしていた去年なら想像もできなかった、光景のかけら。
 長谷の収玄寺の若い紅梅
長谷の収玄寺の若い紅梅
ここに暮らす人たちと、こうしてふいにすれ違う一瞬が好きだ。少し前も記憶の宝箱にいれておきたいすれ違いがあった。鎌倉マダムと呼ぶのがふさわしいような、淑やかで品のある八十代くらいのおばあさま三人組と、鎌倉駅前でふとすれ違った。きっとこの辺りに昔から住んできたんだろうなと思わせる威厳をまとってゆったり歩く姿がきれいで、視界の端にその姿を捉えたときからひそかに見つめていた。すれ違いざま、一人が抑制のきいたハリのある声で言った。「どうせもうすぐ死ぬのなら、○○を暗殺してから死にたいわ。」それはこの一ヶ月間ニュースで名前を聞かない日はない、理不尽な戦争を指揮している人間の名前である。驚くほどたしかな口調でそう言ったのだ!おもわず耳を疑ってしまいそうな、鎌倉マダムの人生の台本には到底書かれているはずのない物騒な台詞である。にもかかわらず、そのことばはちゃんとマダムの日常と地続きの、折れそうに小さな体からこぼれ出たれっきとした現実だった。的をめがけて美しいまでにまっすぐ放たれた一本のいさぎよい矢のような決して冗談には聴こえないその声は、その日じゅう私の体から離れなかった。
 七里ガ浜の凪の海
七里ガ浜の凪の海
東京にいた時にはほとんど聴くことのなかった、声のすれ違いもここにはよくある。「たーけやー、さおだけー」のあれだ。「販売元直売の大安売りです。二本で千円、二本で千円。二十年前と変わらないお値段です。」雨あがりのよく晴れた午前中、洗濯物をやっと干せる安堵感に近隣の何人かの住民が小さな胸をなでおろすタイミングで、大音量のアナウンスを鳴らしながら竿竹屋の車が外をうろうろしはじめる。「古い物干し竿、お取り替えのチャンスですよ!」ですよ、のところがやけに語気が荒いというか、押しがつよくてちょっとこわい。ちなみに、チャンスよと誰かに言われたことが本当にチャンスだったことは今までの人生でほとんどない。
やっと静かになったぁ、と思ったらまたへびのようにうねうね近づいてきて、しばらくするとまたスルスル遠のいていく。そのくり返し。いったいこれを買う人はどれほどいるんだろうか、そもそもどんな人がこういう商売をやっているのかと思いかるい気持ちで検索してみると、ネットの宇宙では竿竹屋さんの正体についてさまざまな憶測が飛び交っていて(実はパトロール中の警察が扮装しているとか、どこぞのスパイなんだとか、詐欺まがいの悪質業者だとかその他諸々。もちろん良心的な業者さんもいるはずですが)、ちょっとした都市伝説になっており真実は闇の中だと思ったので、そっと検索タブを閉じた。
 二階堂の瑞泉寺の花
二階堂の瑞泉寺の花
すれ違いに興味をもったのはちょうど三年前の今頃、台湾にいたとき。三週間の短い滞在のなかば、台南という四月なのにすでに夏真っ盛りの街。ほぼ日課のスコールに降られたその夕方、駅のロータリーそばの地下通路に空気のようにそっと立ち、フルートを吹く女の子がいた。その人の前を通りかかるとき、なぜか私は少しの勇気を出した。この音を聴くために私はふらふら台湾までやってきたのかもしれないという思いが一瞬よぎったのである。名前もしらない彼女がなぜ、その時そこで笛を吹いていたのかはもちろんわからない。彼女の容姿や年幅などはふしぎなほど覚えていない。ただ自分と彼女のあいだに長いあいだ埃をかぶったままの「つながり」のようなものがあり、それが弱い光のようにちらちらと見え隠れするのを感じた。
ふしぎだった。どれだけ一緒の時間を過ごしても、いつまでも遠い人がいる。生まれた時からそばに居続けた血の繋がった人だとしても、いやそうであればこそ、余計につながりを感じにくいこともある。それなのにあの女の子には感じた、記憶とも予感ともちがう妙な「つながり」はなんなのだろう?彼女にまた会うことも、ことばを交わすことも、ただ目の前をすれ違うことさえこの地球上ではもうないに等しいと思うけど、そんなことはまったく問題にならないというような、どんなに面倒くさくても毎秒飽きることなく生まれ変わりながらこれからもつづいていく人生に少しだけ自信を与えてくれるようなもの。
「つながり」は過ごした時間や空間がもたらすものじゃなくて、心と心が反応するその一瞬にある永遠のことを言うのではないかと思ってしまった。そして事実あの「つながり」は今も、うす暗い地下通路を降りしきる雨音のようにごく自然に満たしていた細い笛の音とともに、時おり私の胸のうちに再生され、私をはげましている。

もともと人の中に入っていくのが苦手で、誰かと深くどっぷり濃い時間を過ごすことも少ない。だからかもしれないが、台南の笛の女の子以降、すれ違いには人間同士のこの世の関わり合いにおける重要な何かが隠されているんじゃないか・・・ということを、余白の多い鎌倉にきてからますます思うようになってしまった。すれ違いに何かを探しているのとは違う。あるのはただすれちがうこと、それだけでいいんだという、何かである。あっというまに広がったコロナが世界じゅうの表を裏にし、裏を表にしていったこともおそらく手伝って、体でなく心で共にあるということをより信じるようになったのかもしれない。
この地球上の、地図にたいしてくわしく載ることもない鎌倉の片隅で、どこのだれともわからない人とすれ違う一瞬一瞬が尊くおもえて仕方ない。思ってもみない自然現象のようなものだからすれ違いは美しい。春だからいま余計にそう感じているということはあるかもしれないけれど、それでも日々だれかとすれ違うたび、大切な何かが瞬く間にそっと、無言のうちにやりとりされ、そのことでじぶんの生が少しづつ豊かになっていくような気がする。目もあわさず、この身を決して差しだすこともなく、ひとは確実に一瞬だけ出会う。体はひとつの空間をすれ違ったにもかかわらず、私たちは永遠に出会うことはない。出会わないから、終わりがくることもない。すれ違いは宇宙のスイッチのようなもので、交差を重ねれば重ねるほど生のなかに永遠がふえていく。
 荏柄天神社のミツマタ、あまくていい匂い
荏柄天神社のミツマタ、あまくていい匂い
– にもかかわらず、生きる –
鎌倉に吉野秀雄という歌人が暮らしていたことを先日知った。鎌倉二階堂にひっそり建つ瑞泉寺の、雨風にさらされた古木に彼の詠んだ歌が書いてある。「死をいとひ 生をもおそれ 人間の ゆれ定まらぬ こころ知るのみ」。若い頃から肺結核などの病に苦しみ、何度となく病床に伏せった。長谷に暮らし、七里ガ浜の療養所にも入っていたそうだ。動き回って見た世界よりも、しずかに横臥したまま眺めるしかなかった景色のほうが多い生涯だったかもしれない。それでも生がもたらすよろこびを見出して、できるだけ味わおうとして生きた人のように私には思えた。歌をよむということが、そもそもそういうことなのかもしれないけれど。横臥者には横臥者のゆたかな世界があるのだと同じく体の弱い私は勇気づけられもした。失ったものを眺めても仕方がない。どんな体であろうが目の前にあるよろこびを無為に味わいたい。
この春、新生活が始まろうという人も多い。凝縮された別れと出会いに満たされ、生きものみたいにぱんぱんに弾けそうになった世界は、そして弾けていく。卒業も異動も飲み会もない私に起こるのはきょうもいつもと変わらないぜいたくなすれ違いばかりで、やっぱり春はたのしい。いっぽうで未だ落ち着かない感染症、マスクで遮られてしまった世界の厚さと匂い、忘れたころにやっぱりやってくる地震、海のむこうで無慈悲に消えていく沢山の命、みんなみんなどこへいくのだろう。じぶんにできることは何もない。なぜそれはじぶんではなく彼らの身の上に起こるのだろう?一瞬のことにもかかわらずその後の人生を大きく変えすぎてしまうできごとはなぜ人間の宿命に織り込まれつづけるのだろう?
ほんとうにじぶんにできることは何もないのだろうか?そんなわけない。「ふかくこの生を愛すべし」。吉野秀雄が師と仰いだ會津八一が説いた言葉だ。じぶんの生をほんとうに愛することができたら、それはきっと世界を変える行為になる。できる人がほんの少しいつもより覚悟をもって、愛することをやめず、このなんでもない生に宿る美しさをしっかり見つめていくことができたら…?
 吉野秀雄さんの歌
吉野秀雄さんの歌
また、桜が咲いた。毎年少なくない人がこの花を見上げるたび胸を撃ち抜かれるような思いに襲われるのは、きっとこれが輪廻を形にしたような花だからだろうし、この花を同じようにどこかで見上げているもう会えないかもしれない人の背中を、頭の片隅でそっと抱きしめるからだろう。いのちはいつもどこかへと消え、そしてまたどこからかあたらしいいのちがやってきて、ただそれをくり返す。いのちといのちのあいだに人生がある。

たいして生きてはいなくても、日々沢山のできごとはある。二度とこの世で出会うことのないものや人を思い、時には忘れたり、当然忘れられなかったりしながら、それでも前を向いて歩いていくしかない。失ったものを取り返そうとするのではなく、なかったことにするでもなく、あとはどうにかこうにか工夫して目の前の今を少しでも愛しんで生きる。
ドイツの児童文学作家ミヒャエル・エンデが言った。「希望とは、ものごとがそうであるから持つものではなく、そうであるにもかかわらず、持つ精神なのです」。にもかかわらず朝はくる。にもかかわらず日は暮れる。にもかかわらず人は死ぬ。にもかかわらず、今日私は生きている。自然が私を生かすなら生きよう。それでいいじゃないか。
そういういのちがけの矛盾の中にある隠れた美しさのようなものがこの世界にはあるのだろうから、そういった瞬間をできるだけ真剣に見つけられたらいいと願う。そんなことを思いながら、四月一日がやってきた。

写真・文/ 関根 愛(せきね めぐみ)
関根 愛(せきね めぐみ)